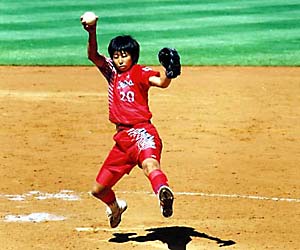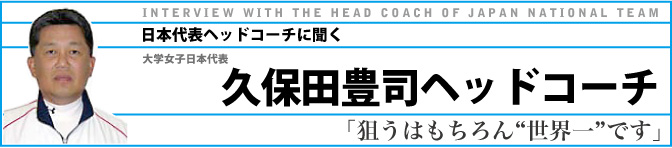
Q1.今回、「ワールドゲームズ 2009」への参加が正式に決定し、大学女子日本代表が大会へ派遣されることになりました。大会への意気込みをお聞かせください。 大学女子のカテゴリーが、ワールドゲームズに派遣されることはたいへん名誉なことと受け止めております。過去の大会において、国際試合に勝つためには、開催地での環境適応、ハードな試合日程の対策、体力面の強化、日本が誇る高い技術力をどう生かすかが課題であると強く感じました。これまでの経験を生かし、ワールドゲームズでは日本代表として自信と誇りを持って戦ってきます。 Q2.今大会での「目標」をお聞かせください。 大学のカテゴリーにおける世界選手権は、過去3大会の戦績はすべて第3位でした。今大会では当然、「世界一」を狙っていますし、大学のカテゴリーとして悲願の初優勝をめざしたいと思います。ワールドゲームズでは、大学のカテゴリーが今まで経験した国際試合の財産を生かし、「優勝」を狙うと同時に、選手には「競技力の向上」のためには、「技術力」だけでなく「人間力」も高める必要があること、そのためには各国の文化を知り、交流を持ち、国際試合とは何かを経験してもらいたいと思っています。 Q3.その上で今回の選手選考会では、どのあたりに選考基準を置き、どんなチームを編成したいとお考えでしょうか? また、コーチングスタッフの人選のポイントなどについてもお聞かせください。 国際試合で勝つためには、「打ち勝つ」のではなく「守り勝つ」ことが勝敗を分ける重要なポイントになります。今回の選考は、得点するためにどう攻撃するのか、自チームの投手力を考え、相手打者に対してどう守るのか、守り勝つ試合をするために実戦での状況判断に優れ、世界で戦う意識の高い選手を選びました。 Q4.久保田ヘッドコーチは、過去3回の世界女子大学選手権をコーチとして、あるいはヘッドコーチとしてチームに携わってきました。そこでの戦いを通じて、大学というカテゴリーの世界的なレベル、国際大会における日本の置かれた立場・位置などについて、印象に残っていることがあればお聞かせください。 アメリカ・オーストラリア・カナダなどの女子大学のチームは、ナショナルチーム強化の段階的なカテゴリーの中の一つとして位置づけられていると強く感じました。それは、女子大学の世界大会に出場した選手が、昨年の北京オリンピックにも多数出場していたことを見ても分かると思いますし、何よりその事実がそれを証明しているといえるでしょう。このことは、大学生が各国のナショナルチームを編成する上で、重要なポジションに位置していること、また、各国がオリンピック・世界選手権に向けて、中・長期の強化・育成が計画されているということの現れでもあります。このことを踏まえ、日本の強化においては、それぞれのカテゴリーの実績を引き継ぐ、カテゴリー間の連携について早急に検討する必要があると思います。 Q5.他国では、「実業団」「企業スポーツ」といったものが存在せず、各国の代表チームの骨格を大学生が担っているチームが数多くあります。そういった中で、日本は「大学」というカテゴリーをどうとらえ、強化していくべきでしょうか? また、「実業団」あるいは「企業スポーツ」とどう関わり、どのような形でお互いを発展させていくべきでしょうか? 女子日本代表の選手は、実業団チーム所属の選手がほとんどです。今後の選手強化において、大学から日本代表へと進むルートを強く太くすることは重要な事項の一つであると考えています。それは高校卒業後に、実業団チーム以外に競技レベルを上げるために大学へ進学し、そこにおいて高校時代より競技力が向上できるなら、新たな強化システムを構築することが可能になるからです。そうすることにより、従来とは違ったルートで今まで以上に幅広い層から有望な人材が発掘され、日本の強化へとつながると思います。そのために全日本大学連盟は、強化委員会を立ち上げ、大学のカテゴリー(男・女)の強化方法について検討中です。 Q6.前回3回の世界女子大学選手権に参加し、大会の雰囲気や運営、参加国の取り組み等で印象に残っている部分はございますか? また、その3大会における世界・国際の技術的な傾向や特徴、日本との差異などを感じる部分はどういった部分でしょうか? 大会運営について、強く印象に残っているのは日本では競技レベルが高くなるほど整備された環境・グランドで試合を行いますが、国際試合では荒れたグランドでも平気でプレーしなければいけません。さらに、地元でテレビ放映される時などは、試合開始時間、イニング間のインターバル等、スポンサー主体の運営であることを強く感じました。 Q7.日本のソフトボールは昨夏の女子日本代表の北京オリンピックに代表されるように、各カテゴリーで輝かしい成果を収めています。今後もこの流れは続いていくと思われますか? また、国際的な競技競争力を維持し、国際的な技術的潮流の中で、日本のあるべき姿とはどうあるべきか、お考えがあればお聞かせください。 国際的な競技力を維持することは、学校運動部と企業スポーツの両輪が衰退しない限り、ある程度は可能だと思います。しかし、この日本型強化システムも、社会情勢の変化と同じで見直す時期が来ていると感じています。それは、フルモデルジェンジではなく、現状の強化システムを点検・評価し、その時代に合ったマイナーチェンジをすることです。そうすることにより、今まで築いた財産に技術的・体力的なこともプラスされレベルアップが図られると思います。また、ソフトボールに関しては、日本は世界の中でリーダーシップを執るべきだと強く感じます。 Q8.今回選出された「大学女子日本代表」の選手たちに、今後何を期待しますか? また、その選手たちに「ワールドゲームズ 2009」への参加を通じて、一番感じてほしいこと、この経験を基にして今後求めていきたいものは何でしょうか? 大学女子日本代表の選手たちには、このワールドゲームズで経験したことを伝え継ぐ「メッセンジャー」として、幅広く活躍することを願っています。また、それぞれの国の文化を知り、人種や民族、国家という枠組みを超えて大勢の人たちと交流を持つことで、「日本のルール」だけでなく「世界のルール」で物事を考えなければいけない必要性を肌で感じ、ソフトボールの強化、普及・発展のために役立ててほしいと思っています。 |
||||||||||||||||||||||